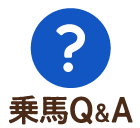【戦国時代の馬文化】武将と共に駆けた忠実なる戦友

ナポレオンにマレンゴという愛馬がいたように、戦国武将にも名馬の相棒がいました。当時、馬は戦いに機動力を与える戦術の一部とされていました。しかし、その一方、戦いから離れれば、馬をパートナーとして大切にしていた武将も多かったようです。今回は馬を愛した戦国武将とその名馬について深掘りしていきたいと思います。
馬上戦の戦術

馬は戦闘の機動力を上げなる戦術上、重要なものでした。馬を戦場に持ち込んだ当初は馬上から弓矢で敵を討つといったシンプルな戦術が取られていました。戦場に適した馬具や馬上から撃つのに適した軽い弓矢などが開発されていたようです。特に現在の山梨県にあたる甲斐(かい)の武田勝頼の騎馬隊は最強と言われており、恐れられていました。
しかし、織田信長がその武田勝頼との「長篠の戦い」で火縄銃を戦術に取り入れたのです。火縄銃は火薬をつめるのに、慣れた兵士でもかなり時間を要しました。火薬をつめている間に武田軍の最強騎馬隊に詰め寄られる可能性があったことから、織田信長は火縄銃を持った兵を列に並ばせ、1回撃ったら後ろに回り、次に自分の順番が来るまでに火薬を詰めるようにするといったいわゆる「三段撃ち」の戦術をとりました(諸説あり)。この戦術によって、武田軍の最強騎馬隊は壊滅的な打撃を受けて敗退します。これが武田一族にとって、衰退の一途をたどる契機になったと言われています。
火縄銃が戦場に取り入れられたことにより、馬上戦の戦術も変化を遂げます。騎馬隊を数隊に分けて、統率をとったうえで襲撃をしかけるなど、さらに機動力を生かした戦略的な戦術に馬を使うように変化していきました。また、騎馬隊に対応する武器も多く開発されていたことから、戦国時代後期には馬から降りて徒歩で突撃する戦法も一般的となっていました。
伝説の軍馬とその武将たち

戦国武将たちにとって、馬は戦友であり、ステイタスでもありました。有名な戦国武将には必ず名馬の相棒がいたようです。なかでも織田信長は馬が大好きだったと言われています。軍事パレードのようなものを開いて馬の品評を行っていました。織田信長の愛馬として有名なのは、伊達輝宗から献上された「白石鹿毛」。奥州では名馬として、とても有名な馬でした。白石鹿毛に限らず、織田信長はとても馬を大切に扱っていたとする文献が残っています。
豊臣秀吉にも名馬の相棒がいました。よく知られているのは奥州驪(おうしゅうぐろ)です。農民の出であった秀吉は、出兵の際に馬を1頭工面するのにも非常に苦労したと言われています。しかし、みるみるうちに出世を重ねて、奥州驪と出会うのです。奥州驪はその名の通り、真っ黒な奥州馬でした。秀吉を乗せて、短時間で25里(約100キロ)も駈けたとも言われています。また、もう一頭、豊臣秀吉の愛馬として有名なのが、内記黒(ないきぐろ)。秀吉から長曾我部元親に与えられた芦毛の名馬で、元親を乗せて戦地を駆け抜け、その命を救ったという逸話があります。内記黒は高知市に残る元親の墓に近い「愛馬之塚」に葬られていると言われています。
徳川家康は「海道一の馬乗り」と言われるほど馬術に長けた武将でした。家康が所有していた名馬と言えば、「白石」と言われるほど有名なのだそうですが、意外にもその詳細は後世にあまり伝えられていません。静岡県浜松市には「馬冷(うまびやし)」という地名が残っています。戦いが続き、人も馬も疲れていた際、この地域にあった池で「馬を冷やせ」と家康が命令したことが由来となり、今も地名として残っていると言われています。
現代に残る馬文化

流鏑馬の由来は諸説ありますが、6世紀ごろに五穀豊穣を祈願して、欽明(きんめい)天皇が行った神事に由来しているのではないかと言われています。平安時代では宮廷の催しものとして発展し、鎌倉時代には源頼朝が積極的に取り入れたことから、武芸として発展していきます。しかし、戦国時代のころには、集団的な戦法をとることが増えた戦いに、個人で行う流鏑馬のような武芸は活かせないと一時衰退していきます。江戸時代の徳川吉宗の時代にまた復活をして、現代に至ります。
福島県で行われる相馬野馬追は、平安時代に平将門が野生馬をとらえ、奉納したことが由来とされています。これに倣い、馬を野に放ち、馬を敵兵にみたてて、軍事的な演習をするようになり、発展していきます。平将門が亡くなった後は相馬家が引き継いで行われていました。しかし、平和な江戸時代に入ると軍事的な演習の意味合いは薄れて、祭礼として行われるようになっていきます。野馬追には、唯一、古式の名残がある野馬懸に神旗争奪戦や甲冑競馬が加わり、現代の野馬追へとつながっていきます。
まとめ
今回は戦国時代の馬についてや戦国武将の愛馬たちについて深掘りしてみました。東西問わず、戦がたくさん行われていた乱世では、武将やリーダーには必ず名馬の存在がありました。戦場で乗るためのものだけではなく、自身の愛馬として手厚く世話をしていた武将が多かったようです。その背景には、人間は裏切るが、馬は裏切らないといった考え方があったのだとか。厳しい時代にあっても、苦楽を共にする人馬の絆は固く結ばれるものなのですね。