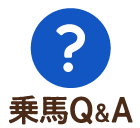日本在来馬の歴史

皆さん、日本在来馬の存在をご存じでしょうか。人間と馬、種は違えど日本で暮らしてきた者同士、「日本在来の」と言われると何だか親近感が湧いてきますよね。しかし今では頭数が少なく、わたし達が目にする機会はそれほど多くありません。古来より日本で生き抜いてきた在来馬達。まずは日本在来馬を知るところから始めてみましょう。
日本在来馬とは

日本在来馬とは古くから日本にいる馬種で、洋種馬などの外来種と交配することなく現在まで日本で残ってきた馬種です。明治以降は大きな馬格を持つ西洋の馬が好まれるようになり、在来馬の多くが外国から来た馬と交配し改良が行われた結果、日本在来馬として現存しているのはわずか8品種のみとなってしまいました。
北海道和種(道産子):1087頭
北海道を中心に飼育されている品種で、道産子と呼ばれ親しまれています。頭数は日本在来馬の中では最も多く、馬体も比較的大きいのが特徴。江戸時代、夏に使役する為に南部から連れてきた馬がそのまま放置され、北海道の気候風土に適応するようになったのが北海道和種の先祖だと言われています。
木曽馬:133頭(長野県の天然記念物)
長野県の木曽地域や岐阜県の飛騨地方を中心に飼育されています。木曽馬はぽこっと出たお腹が特徴の一つなのですが、これは他の馬種よりも盲腸が平均で30cmほど長く、太さも約2倍もあるからだとか。その為木曽馬は粗食で、草だけでも生きていくことができるそうです。
野間馬:48頭(今治市の天然記念物)
野間(愛媛県今治市)で主に飼育されています。江戸時代に合戦用の馬を松山領野間郡の農家に育ててもらった際、戦では活躍が難しい体高の低い馬を農家に無料で払い下げた事で体高の低い馬同士の交配が進み、今のような小さい野間馬ができたと言われています。
その後は国が小型馬の生産・育成を禁止したり、車や機械により活躍の場が奪われたりと、頭数は年々減少。昭和30年代にはとうとう今治市に野間馬は1頭もいなくなり、やがて日本全土でも6頭だけとなってしまいます。
ですが松島市で飼育されていた大変貴重な4頭の野間馬が今治市に寄付され、今治市では早速「野間馬保存会」を作って継続的な保護活動に取り組んでいます。
御崎馬:98頭(国の天然記念物)
宮崎県串間市の都井岬に生息しています。都井岬に牧場が開設されて以来300年以上もの間、人の手をほとんど加えず一年を通して放牧される周年放牧という飼育方法が取られています。育成と繁殖が自然に任され、死んでも埋葬などはせずにそのまま土に還るようにしています。ここではまさに自然の中、本来の姿で生きる馬の姿を見ることができます。
御崎馬は自然育成の為、乗馬としては使用されておらず触れることや近づくことは禁止されているので、見学する時は遠くから見守って下さいね。
対州馬:45頭
長崎県対馬市を中心に飼育されてきた日本在来種。対州馬は古くから対馬で飼われていて、鎌倉時代の元寇(モンゴルとの戦)の時に武将を乗せて活躍したと伝えられています。対州馬もやはり車や機械の普及でその役割を失い、島内での生産がされなくなった事から数が減っていきました。現在では対馬市が担う対州馬保存会により種の保存、対州馬の普及啓発の取り組みを行っています。
トカラ馬:85頭(鹿児島県の天然記念物)
鹿児島県のトカラ列島(鹿児島郡十島村)で飼育されてきた品種です。驚いた事に1952年に確認され日本固有の純粋種として認知されるまで、全く世間に知られずに生息していました。元々は喜界島からサトウキビ栽培のための労力として渡って来たようです。現在は人の手をあまりかけず、昼も夜も年間を通して放牧されています。
他の日本在来馬と違い、トカラ馬は乗用馬としては使われず観光などへの利用についても方針が定まっていない状況下にあり、トカラ馬の活用は今後の保護の上で大きな課題になっています。
鹿児島市平川動物公園や恩賜上野動物園で飼育・展示がされているので、会いに行ってみるのもおすすめですよ。
宮古馬:48頭(沖縄県の天然記念物)
沖縄県宮古島で飼育されています。明治時代に宮古島でサトウキビ栽培が始まると宮古馬がその農耕に活躍しました。その他にも琉球王国時代に行われていた沖縄の伝統的な競技「琉球競馬」に使われていたり、琉球王朝の公用馬として能力を発揮していました。
与那国馬:110頭(与那国町の天然記念物)
沖縄県の与那国島で飼育されています。日本最西端の離島である与那国島に生息している為、品種改良や他の品種との交配が行われずに与那国馬独自の系統が保たれてきました。宮古馬と同様に沖縄の伝統的な競技である琉球競馬に使われ、今は主に乗馬や観光などに活躍の場を移しています。
2024年の農林水産省の報告では、各在来馬の保存会による保護活動で飼養頭数は横ばいまたは微増となっているものの、まだまだ楽観視できない状況が続いているとの事です。
いつ頃どこからやって来たの?

馬は大昔から人々の生活に欠かせない存在だったと言われていますが、実は古墳時代より前、日本に馬はいなかったようです。どのようにして日本にやって来たのか、それは日本の朝鮮半島進出が大きく関わっています。
4世紀後半、朝鮮半島の高度な文化や豊富に採れる鉄などの資源を求め、当時の日本は朝鮮へ進出していきます。この頃の朝鮮半島では、高句麗・百済・新羅・伽耶という4つの国で覇権争いが繰り広げられており、日本は交流のあった百済と同盟を結び、高句麗と戦う為に朝鮮半島へ赴きました。
そこで遭遇したのが高句麗の騎馬軍団。その騎馬戦力の高さを目の当たりにし、戦いに馬を使う必要性また移動手段としての有用性を痛感したようです。
友好関係にあった百済の協力のもと、東アジア諸国と渡り合う為にモンゴル高原から朝鮮半島を経て馬を導入し、国策として馬産地を各地に展開していきました。百済や伽耶は日本に専門家を派遣するなど大規模な馬産地作りに協力し、馬具の生産技術などを教えたと言います。
時代とともに変化していった役割

馬はその導入の経緯からも分かるように、当初は軍事的な役割を持っていました。
5~6世紀以降になると民衆統治制度に「品部」と呼ばれる技術を以て朝廷に奉仕する組織が編成され、渡来人が主導する馬の専門集団もここに配置されました。彼らは馬を飼育し、繁殖させ、こうして本格的な馬の国産化が始まります。そして馬を調教する事で、人を運ぶ乗用馬、労力の代替として荷物を運ぶ荷馬や田畑を耕す農耕馬、神様へ奉納する御神馬など、役割の幅も広がっていったのです。
このように今に残る日本在来馬は長きに渡り、その時代の流れによって役目を変えながら人々の生活や文化に寄り添ってきたのでした。
まとめ
日本在来馬の貴重さやその歴史を知ると、種の保存とはただ単純に繁殖・飼育するのではなく、その時代に合った活躍の場を見出す事が必要なのだと感じますね。彼ら彼女らは日本の長い歴史においてその血統を受け継ぎ、奇跡的にも現在へと繋げてくれました。もちろん純血種が絶滅してしまっている種もあります。だからこそ今後も現存する日本固有の馬たちを守っていければと思います。