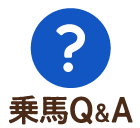馬型新ロボット「CORLEO(コルレオ)」とは

世界中にファンを持つバイクメーカーの川崎重工が四足歩行の馬型ロボットのコンセプトモデル「CORLEO(コルレオ)」を開発し、大阪・関西万博で展示しました。乗り物を操縦する楽しさを提供してきたメーカーが、操縦の楽しさをそのままに安定性を重視し、悪路も安全に移動できる高い走行性を再現した駈けるロボットです。人間の「移動本能」や「Fun to Ride」をテーマにデザインされています。
どんなロボット?
「コルレオ」はcore(核)とleo(獅子)をくっつけた造語で、「技術の中心であり、時代の先頭を歩く獅子」を意味しています。コルレオは人間の持つ「移動本能」の喜びを刺激しながら、岩場などの足場のよくないところや災害地での救助活動でも運転できるよう多用途を目指して開発されたパーソナルモービリティロボットです。
その外見はバイクとライオンを合体させたような雰囲気です。馬に騎乗するように跨って、ハンドルとステップ(鐙にあたる部分)に対する重心の移動で進行方向に操作できます。ロボットの前肢と後肢は別々に動くため、走行時のショックを吸収できる乗り手にも優しいつくりです。
四肢の先には「ひづめ」もついています。この「ひづめ」には滑りづらいラバーが使われており、「左右二分割構造」を採用したことから、草原、岩場、がれ場など様々な地面に対応できるようになっています。開発にあたり、動物すぎず、マシンすぎずの絶妙なラインで開発を進めたそうです。そのため、尾などの動物らしい要素は削られた部分も多いのだとか。
このロボットには、150ccの発電用水素エンジンが採用されています。水素を使用して、エンジンで発電された電気が、四肢に設置したパワーユニットの動力になり、四肢を動かしています。また、頭部にあたる部分には水素残量、ルート、重心位置などが表示されるつくりになっており、スムーズな操作をサポート。また、夜間は進行方向に進路を示すマーカーが点灯するため、暗闇中での運転も安心です。
重心の移動で進行方向を定めるなど、馬乗りが好きな皆さんにはピッタリのロボットなのですが、コンセプトモデルであるため、試乗はできません。また残念ながら実用化は未定です。
活躍が期待される場

車輪では、プロでも走行が難しいボコボコした悪路でも、「ひづめ」のおかげでプロではない「ライダー」でも問題なく安定した運転が可能です。草原を馬のように駈けるのはもちろん、山岳地帯や水場も走行できるので、実用化が進めば、趣味の用途に限らず、遭難者や被災者の救助に活用できる心強いロボットになるかもしれません。
車が通過できないような狭い場所を移動したい場合でも、コンパクトで機動力の高いこのロボットであれば、進んでいけるでしょう。また、生き物である馬の場合は道中に何か突発的なことが起きた場合、びっくりして暴れてしまったり、体調を崩してしまうこともあるかもしれません。しかし、このロボットを使えば、例えば余震や予期しない音などでびっくりすることもなく、水素があれば安定した走りが期待できます。
もちろん、現時点では実用化への課題がいくつもあります。エンジンの原動力になる水素を補充できるスタンドは徐々に増えてきてはいますが、それでもガソリンスタンドのようにすぐに補充できないエリアがあることは、実用化の大きな課題になるでしょう。さらに公道などで走行するためには、法律の整備を進めていかなくてはなりません。2050年に実用化を目指しているという話もささやかれているため、少しずつ整備されていくことに期待したいですね。
また、実用化に近いレベルとされるプロトタイプがまだ開発されていないことから、実用化にはさらに開発と研究が必要となり、かなりの時間を要すると考えられます。
大阪万博で展示
コルレオは大阪・関西万博の「未来の都市」パビリオンで初めて展示されました。同パビリオンでは、地域課題や社会課題を解決するための発明を展示しています。2030年代の仮想都市をテーマにしています。
今回のパビリオンでは残念ながら、試乗することは叶わなかったようですが、歩いているところやポーズをとっているところを見学することはできたそうです。反響が大きかったら、実用化に向けて開発を本格的に進めていく可能性もあるかもしれないとのこと。いつか、実際に馬と乗り比べてみたいですね。
まとめ
マイアミ大学の論文では、「人は移動するほど幸せを感じる」という研究結果が発表されています。コルレオのコンセプトモデル開発では、人間が持つと考えられる「移動本能」を刺激することを重視しました。家族や友人たちとツーリングさながらに安心して山岳地帯を駆け抜けることができたら、旅がどれだけ楽しいものになるでしょうか。また、実用化が叶えば、足場の悪い被災地での救助活動等にも活用できる算段が大きいのだろうと考えます。
しかし、それと同時に、「乗馬愛好家」である私たちは、馬たちの「面倒くささ」や「体温」、「におい」といった「生の刺激」からも逃れられないのかもしれないと思いを馳せました。