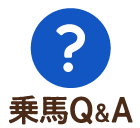馬への負担が少ない「モンキー乗り」

競馬の騎手は、走っているあいだほとんど鞍におしりを着けずに、しゃがんだような姿勢を保っていますよね。この乗り方を「モンキー乗り」といいます。モンキー乗りは、単に見た目が特徴的なだけでなく、馬の走行性能や疲労の軽減にも関わる高度な技術。今回は、このモンキー乗りの特徴や歴史について解説していきたいと思います。
「モンキー乗り」とは

モンキー乗りとは、鐙(あぶみ)を短くし、膝を大きく曲げて前傾姿勢をとりながら鞍に座らずに騎乗するスタイルを指します。その姿が、まるで猿(モンキー)が木の枝にまたがっているように見えることからこの名がついたといわれています。
乗馬をしたことがあれば「ツーポイントと似たようなもの?」と少し想像ができるかもしれませんね。乗馬では、普段は鐙に乗せた両足と鞍に着いたお尻の“スリーポイント”で体重を支えていますが、障害物を飛ぶ瞬間などはお尻を上げてやや前傾し、鐙に乗せた足だけの“ツーポイント”で体重を支えます。
レース中、常にその姿勢を保つことや前傾姿勢の強さなど乗馬のツーポイントとは異なる点もありますが、姿勢により馬の負担を軽減するという意味では近いといえるかもしれません。
歴史

(投稿者が出典書籍より取り込んだ画像です – 『日本ダービー25年史』(日本中央競馬会、1959年))
今や競馬界では当たり前になっているモンキー乗りですが、以前の日本では競馬であっても鐙は乗馬するときのように長く、お尻を鞍に着けて上体を起こした“天神乗り”が主流だったそうです。では、モンキー乗りはどこで生まれて、どのように日本にやってきたのでしょうか?
起源はネイティブアメリカンの騎乗法?
モンキー乗りの起源ははっきりわかっていませんが、少なくとも18世紀には一部の黒人騎手が採用しておりネイティブアメリカンの騎乗方法を参考にしたものではないかともいわれています。しかし、当初は一般的なものでなく、競馬界に広く取り入れられたのは1890年代。きっかけは、トッド・スローンという騎手の活躍でした。
スローンは、馬の動きを可能な限り邪魔せず体力消耗を抑えるために、鐙を短くし、重心を前方に移しながら馬と一体化するようなフォームを採用。当初こそ「え?何あの姿勢……斬新すぎない?」と奇異の目で見られたそうですが、レースでの好成績が注目され、徐々に受け入れられたようです。
日本への伝来と普及
日本にモンキー乗りが広まったきっかけは、1950年代後半。国内競馬で優秀な成績を収めていたハクチカラのアメリカ遠征です。騎手・保田隆芳がともに渡米し、現地でモンキー乗りの技術に触れました。
それ以前にも外国人騎手によってモンキー乗りに近い騎乗方法が国内で紹介されて、その技術を参考にしていた日本人騎手はいたようです。しかし、実際に日本人が本格的なモンキー乗りを習得したのはこれが初めてだったといわれています。
帰国後、保田騎手はこの新しい騎乗スタイルを日本の競馬界に紹介。まだ天神乗りが主流だった当時の日本において、モンキー乗りは革新的な技術でした。以後、日本の競馬も世界の潮流に追いつく形でモンキー乗りが主流となり、今ではすっかり定着しています。
普及した背景
ここまで紹介したように、モンキー乗りは今でこそ競馬では当たり前の乗り方と認識されています。しかし、当初は「変わった乗り方」としか思われていなかったでしょう。それが今となっては世界中で受け入れられているのは、そこに確かな合理性があったからです。
2000年代に発表された研究では、モンキー乗りによって馬の走行速度が5〜7%も向上したというデータがあります。
馬は走る際に背中が上下に動くため、かつて日本で行われていた“天神乗り”では騎手もその動きに合わせて上下してしまいますよね。すると、馬は重心がぶれて体力を消耗してしまいます。
みなさんも荷物を持たずに走るよりもリュックを背負って走るほうが走りにくいと思いますが、これは「重いから」だけでなく「自分の重心とは別にリュックの重心が移動して邪魔してくる」からなんです。
一方、モンキー乗りでは騎手が膝の屈伸を使い、自身の上下動を最小限に抑えることで、馬の動きに干渉しにくくなります。その結果、馬の負担が減って効率的に走るれるようになります。
乗り方のコツ

モンキー乗りは合理的な騎乗方法ですが、常に低い中腰のような姿勢を保つ筋力や、足だけに体重を乗せて前後左右のバランスを保つ高度な技術が必要です。実際にやる場面は少ないと思いますが、モンキー乗りにはどのようなコツがあるのか見てみましょう。
鐙の長さを調整する
モンキー乗りの第一歩は、鐙の長さの調整から始まります。通常の乗馬に比べて、鐙をかなり短めにすることで、膝を深く曲げた姿勢を取りやすくなります。
このときのポイントは、「バランス」です。鐙が短すぎるとバランスを崩しやすくなり、逆に長すぎると膝が伸びてしまい、効果的な前傾姿勢が取れません。自分の体型と脚力に合わせて、最適な長さを見つけていくことが大切です。
鞍に座らず、腰を浮かせる
モンキー乗りの最大の特徴は、鞍に座らずに腰を浮かせる点です。ここでも膝の屈伸が重要になります。馬の動きに合わせて、膝を伸ばしたり曲げたりすることで、騎手の重心の高さを一定に保つよう意識しましょう。
また、腰を浮かせた状態では上体を前傾させて重心を馬の前方へと移動しつつも、前脚ばかりに負担がかからないよう鐙の上でしっかりとバランスを取ります。これにより、馬の推進力を最大限に活かすことができます。
バランスを保つための練習
モンキー乗りは、静止状態でのフォーム確認だけでなく、実際の走行中にバランスを取る練習が不可欠です。特に、前後左右の動きに対する反応力を養うには、速歩や駈歩の練習を通して体を慣らしていく必要があります。
まとめ
モンキー乗りは、騎手が筋力・バランスを取る技術などを身に着けることで馬への負担を最小限に抑える騎乗方法です。
競馬の騎手は当たり前のようにやっていますが、実際にやってみたらすぐに全身が筋肉痛になること間違いなし。また、乗馬の鐙の長さに慣れている人は、モンキー乗りの鐙の長さで騎乗すること自体「こわい」と感じるかもしれません。
実際にやることがなくても、どのような技術か知ることで次に“モンキー乗り”を見たときの見方が少し変わるかもしれませんね。