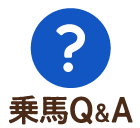よく使われる「馬」の慣用句・ことわざ

馬と人間は昔から助け合ってきました。生き残るために、お互いを必要として関係性を築き上げてきたからなのでしょうか。普段、何気なく使っている言葉の中にも馬に由来する言葉は意外と多い気がします。今回は、そんな馬に関する慣用句やことわざをご紹介します。
馬子にも衣装

「馬子にも衣装」は「どんな人でもそれなりの身なりをすれば、立派に見える」という意味のことわざです。「孫」にも衣装は誤用です。「あの人は普段、あんなに地味な人なのに、今日はとても立派に見える。馬子にも衣装なのね」といった使い方をします。
江戸時代には、すでに使われていたと言われています。馬子とは、馬で荷物や人を運ぶことを職業としていた人たちのことをさします。普段は汚れがちな作業着を着ている馬子のような人たちでも、身なりを整えれば立派に見える、というのがその語源です。つまり、馬子はあまり目立たない身分の低い人の代表例として、使われていたようです。この言葉ができた時代では、身に着けているものを見れば、地位や立場が今の時代以上にはっきりと分かる時代だったことが想像できますね。ただし、人の見た目に関する慣用句ですので、現代ではハラスメントになってしまうかもしれません。使い方や使う場所を間違えてしまうと、失礼な印象を与えてしまう可能性もあるので、気を付けましょう。
同じような言い回しは英語にもあります。Fine feathers make fine birds. 直訳すると「羽毛が立派であれば、鳥も立派になる」。つまり、身に着けているものによって立派に見える、という意味になります。同じような言葉でも、西洋では「馬」や「牛」ではなく「鳥」を使っています。種類は違いますが、動物をたとえに使っているところが東西で共通していて面白いですね。
馬の骨

「どこの馬の骨とも知らない奴に娘をやれるか!」といったセリフをドラマなどで聞いたことはありませんか。「馬の骨」は、素性の分からない人という意味で使われます。もともと、「馬の骨」は中国で「役に立たないもの」を意味する言葉でした。「一に鶏肋、二に馬骨」という言葉が由来とされています。「鶏の肋骨は小さすぎて役に立たず、馬の骨は大きすぎて役に立たない。それどころか処分にも困る」という意味だそうです。これが転じて、よく素性の分からない人間に対して使うようになりました。
また、馬の骨の油から作った粗悪なロウソクのことも昔は「馬の骨」と呼んだのだそうです。いずれにしても、馬の骨は厄介もの扱いをされていたのは間違いないようですね。
「馬の骨」が使われ始めたのも江戸時代からと言われていますが、当時は「牛の骨」も同じ意味で使われていたそうです。牛や馬が人間にとって身近な存在である動物であったことから、「牛の骨」や「馬の骨」と言われるようになったのではないかとされています。
馬車馬のように働く

「自分は馬車馬のように働いている」と友人から聞いたら、ブラック企業で過酷な働き方をしているんだな、と気の毒に思いませんか。しかし、実際は「わき目もふらず、一生懸命に働く」ことを意味する慣用句です。友人は自虐を言ったわけではなく、自分は前向きに仕事を頑張っているのだと話しているんですね。
馬車馬の頭絡には目隠し(ブリンカーとも言います)がついています。目隠しをすることによって、馬は物見をせず、仕事に集中してまっすぐに走ってくれるのだそうです。その馬車馬の様子から「馬車馬のように働く」という言葉が生まれたのだそうです。「馬車馬のように働く」と聞くと筆者は「黒馬物語」の辻馬車の馬たちを思い出してしまいましたが、これは正しい認識ではありませんでした。
馬脚を露わす

「馬脚を露わす(あらわす)」は、包み隠していた正体や悪事がばれてしまうことを意味します。今まで隠していた本性を現したときなどに「あの人はとうとう馬脚を露わした」といった使い方をします。似ている言葉に「化けの皮が剝がれる」があります。語源は舞台で馬の脚役を担当していた役者がミスをして、脚役の自分が観客にさらされてしまったことに由来するそうです。「露わす」が常用漢字ではないことから、現在では「馬脚を現す」と表記されることが多いようです。「馬脚を出す」もよく使われているそうですが、こちらは誤用なので要注意。「尻尾を出す」と混同された誤用と言われています。
「馬脚を露わす」も、もともとは中国のことわざです。出典は元の時代の古典劇「包待制陳州糶米(ほうたいせいちんしゅうちょうまい)」にある「露出馬脚来」。のちに日本でも「馬脚を露わす」と使われるようになりました。
まとめ
いかがでしたか。今回は「馬」に関係のある慣用句やことわざについて深掘りしてみました。他にも「埒(らち)が明かない」や「馬の耳にも念仏」など馬に関係のある慣用句やことわざも多く、人間と馬の関係性が深かったことが分かります。ただ、ポジティブな印象の言葉があまり多くないのが、どうしても不思議でなりません。