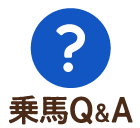歴史からみる「馬」と「人」の関係性

みなさんも、中世を取り扱った洋画のほかテレビの時代劇などを見て「今よりずっと馬が身近だったんだな」と感じたことがあるかもしれません。今回の記事では、人と馬の歴史はいつごろから始まり、日本ではどのような歴史があったのか紹介していきます!
馬と人の関係はいつから?

人と馬の関係はとても古く、どの時代から始まったのかを正確に知ることはできていません。しかし、世界各地の遺跡で発見された壁画や道具などから、その歴史が少しずつ分かってきています。
世界での起源
人が馬と密接な関係にあったことを裏付ける遺跡としては下記が有名です。
- フバリンスク遺跡(ロシア)
- デレイフカ遺跡(ウクライナ)
- ボタイ遺跡(カザフスタン)
遺跡から出土した馬の骨や道具を調べると、紀元前4500年ごろには馬が狩猟の対象になったり飼育されたりしていたらしいこと、紀元前3500年ごろにはすでに馬具によって馬を制御したり騎乗したりできたことがわかるそうです。
人よりも力があり長距離移動も可能な馬は、そこから交易や戦争にも利用されるようになります。
その結果、馬の飼育技術・騎乗技術を磨くことが重要視され、紀元前300年ごろの古代ギリシャでは哲学者であり軍人だったクセノフォンによって最古の馬術書が執筆されたのだとか。どんな内容だったのか気になりますね。
こうした流れを汲みながら、時代が下ると騎乗技術は軍人や貴族を中心に一種のたしなみとされ、現在のブリティッシュスタイルの乗馬のように馬を制御する技術を披露するものとなっていったようです。
日本に馬がやってきた時期
国外と比べると日本人と馬のかかわりは歴史が浅く、埴輪や古墳の出土品などから弥生時代の末期に朝鮮半島経由で馬や馬具が持ち込まれたと考えられています。
つまり、日本人にとって馬は狩猟動物から家畜化を経て…というわけではなく、最初から「乗用の貴重な動物」という位置づけ。ごく限られた階級の人が所持している特別な財産でもあったと考えられます。
そして時代が下ると、国内で馬の生産もできるようになり貴族や武士を中心に馬を所持する人が増えていきました。
乗馬がスポーツに

人が馬に乗り始めたころは、産業や戦争を有利にするために必須ともいえた騎馬技術。では、いつ頃から乗馬は「スポーツ」として楽しまれるようになったのでしょうか?
ヨーロッパでの発展
乗馬には大きく分けてブリティッシュスタイルとウエスタンスタイルがあります。このうち、ブリティッシュスタイルはヨーロッパで発展したもの。
中世に入ると騎士という身分が生まれ、武芸として騎乗技術が磨かれました。その後、ルネッサンス期になるとイタリアでクセノフォンが再評価されたことに始まり、フランスの“現代馬術の父”ド・ラ・ゲリニエールがこの流れを完成させたそうです。
このころの知識や技術は現代の乗馬の基礎を形成。その後もドイツやオーストリアなどヨーロッパ諸国は著名な馬術化を輩出し、同時に騎乗技術も洗練されたものになっていったのだとか。
こうして「ブリティッシュスタイル」が確立され、やがて世界中に広まっていきました。ブリティッシュとはいうものの、ヨーロッパのさまざまな国のかかわりの中で完成したスタイルと言えそうですね。
アメリカ大陸のカウボーイ文化
一方、アメリカ大陸で発展したのが「ウエスタンスタイル」。なんとなくイメージが付くかもしれませんが、カウボーイ文化から生まれたスタイルです。
アメリカ大陸では16世紀にスペイン軍がメキシコに上陸。これをきっかけに騎乗技術や馬が持ち込まれ、牧畜のために馬を駆使するカウボーイ文化が生まれたといいます。
カウボーイは牛を追い、長時間・長距離にわたって馬に乗る必要があったため、そこから生まれた騎乗技術も快適さや効率・機動性などを重視したもの。この技術を娯楽的に競っていたものが、ルールが整備されて「ウエスタンスタイル」の競技になったとされています。
日本に乗馬が浸透した時期

まだまだ乗馬先進国の欧米に比べると乗馬の競技人口が少ない日本。スポーツとしての乗馬は、いつ頃からどのように浸透していったのでしょうか?
明治から戦前まで
外国での流れを見ると、もともとは軍事的・職業的に必要な技術をルールのなかで競うようになったのがスポーツ乗馬の始まりと言えそうですね。
日本にも流鏑馬や打鞠といった伝統的な馬術文化があり、武芸の一部として長く受け継がれてきました。武士や貴族のあいだでは、これらが娯楽的に行われたりもしたようですが、現在のような西洋式の乗馬が日本に入ってくるのは江戸時代のこと。
江戸末期になると幕府軍にフランス式の騎兵隊が作られるなど西洋の馬術が導入され始めます。さらに、軍事目的で乗馬技術の研鑽が始まり小柄な日本在来馬にかわり洋種の馬が育成されるようになりました。こうした背景もあり、幕末から戦前にかけては乗馬といえば軍人など限られた職業のみが身につけていた技術だったようです。
戦後から現在
戦後、日本が国際社会に復帰するなかでオリンピックへの参加が再開されたことで、競技馬術の世界は一般の人にも開かれたものになり始めました。これが1950年代のことなので、日本での競技馬術の歴史は世界的にみるとかなり短いことがわかりますね。
とはいえ、2012年のロンドンオリンピックでは当時71歳だった法華津選手が出場して「乗馬って、かなり長く現役として楽しめるスポーツなんだ」と広く知られたほか、2024年のパリオリンピックでは総合馬術で日本代表が銅メダルを獲得するなど国内での注目度も徐々に上がってきているはず。
まだまだ競技人口が多いスポーツとは言えませんが、だからこそ、これから国内でどんな広がりがみられるのか楽しみでもありますね。
まとめ
なんとなく「馬って昔から日本にいたんだろうな」と思っていたみなさん、いかがでしたか?実は、馬自体も乗馬技術も時代ごとに外国から流入していたと知るとちょっと意外な気持ちになるかもしれません。
日本では、車などが使用されるようになってから労働力・移動手段としての馬は生活になじみがなくなりましたが、競技としての乗馬が広がることで馬が「生活や仕事の一部」だったころとはまた違う馬との関係性ができていきそうですね。
今では国内でも乗馬クラブや乗馬用品メーカーが増えて「挑戦したい」と思ったらチャレンジできるスポーツになってきたので、「興味はあるけど体験したことはない…」という人は、ぜひ近くの乗馬クラブなども探してみてはいかがでしょうか?