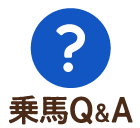馬が由来となった意外な言葉

私たちが日常的に使っている言葉の中には、意外にも「馬」に由来するものが数多くあります。現代では馬が交通や農作業の主役ではなくなったので、こうした言葉を「馬に関する言葉だった」とは知らないまま日常生活の中で頻繁に使っている……なんてこともあるかもしれませんね。今回は、そのなかで「コーチ」「はなむけ」「バテる」「埒があかない」という4つの言葉をピックアップして、その由来について紹介します!
コーチ

「コーチ」と聞くと、多くの人はスポーツなどの指導者を思い浮かべるのではないでしょうか?しかし、この言葉のルーツは地名。では、この地名が馬とどうかかわっているのかみていきましょう。
「コーチ」という言葉は、もともとハンガリーのコチ(Kocs)という地名に由来しています。コチでは、15世紀に金属製のバネをサスペンションとして使用した馬車を製造開始。この画期的な仕組みと品質の高さにより、周辺各国で一躍有名となりました。
サスペンション付き馬車は、その他の馬車と区別して「コチの馬車(コチ・セケール)」と呼ばれ、これが一般化していくとともに馬車そのものを「コチ」と呼ぶようになったといいます。この「コチ」を英語で「コーチ」と発音します。自動車が馬にとってかわった現在でも、英語圏では長距離バスのことを「コーチ」と呼ぶ地域があるそうですよ。
「乗物だったものが、なんで今の意味になったの?」と疑問に思うかもしれませんが、馬車は歩くと大変な距離も、人間を乗せて運んでくれますよね。このイメージから、一人ではたどり着くのが困難なゴールへ導いてくれる人のことをコーチというようになったんです。
はなむけ

「はなむけの言葉を贈る」といった表現は、少し古い言葉かもしれませんが今も耳にすることがあるでしょう。特に、卒業や異動のシーズンとなる春にはよく聞く言葉ですね。
現在では、はなむけといえば感謝や激励の意を込めて相手に贈る言葉や品物を指します。「はなむけ」には餞別の「餞」という字があてられることもありますが、語源がわかりやすい表記は「鼻向け」でしょう。
古くは旅立つ人を見送るときに、馬の鼻先をその人の目的地の方角へ向けることで、道中の安全や無事に到着することを願う風習がありました。これを、「馬の鼻向け」といいます。
現在は馬を飼っている人も少ないので、実際に馬の鼻向けを行う機会はほとんどなくなり、物や言葉を贈るという形になりましたが……。新しいスタートを切る人を思う気持ちとともに、言葉としての「はなむけ」はしっかり残っています。
バテる

「そんなに頑張ると、途中でバテちゃうよ」「最近の夏は暑すぎてすぐバテてしまう」といったように、バテるという言葉を使う機会は多いのではないでしょうか?
バテるの語源には諸説あり、定説となっているのは「果てる」。体力や気力を使い果たし、勢いが衰えたり動けなくなってしまったりするという意味だろうと考えられています。
そして、「果てる」ほど有名ではないですが馬に関係する語源も。それは、馬が疲労して脚運びが悪くなった歩行状態を表す「ばたばたする」が転じてバテるになったというものです。無理があるようにも感じますが、ひどく疲れたことを「今日はもうバテバテ」と言ったりすることを考えるとちょっと納得感があるかもしれませんね。
ちなみに、バテるという言葉は人間にもよく使いますが、もともとは「馬が疲れて動きが悪くなる様子を表す」ときに限定して使われていたようです。
近代では競馬で体力配分がうまくいかず終盤に力を発揮できない馬の様子を指し、戦後に競馬が公営化され広く楽しまれるようになったことで「バテる」という言葉が広まったのだとか。そのほか、時代が下るにつれて馬に限定せずスポーツ選手にも用いられるようになり、そこから一般化したという説もあります。
埒があかない

物事の終わりや解決の糸口が見えないときに「いくら話し合っても、埒(らち)があかない」なんて言ったりしますよね。埒とは囲い・柵といった意味があり、それが転じて物事の区切り・限界などの意味で使われることもある言葉です。
この用法で「埒があかない」を考えると、そのまま「区切りがつかない・終わりが来ない」といった意味だとわかりますよね。それに加えて、埒が特に馬の行動範囲を制限するための柵を指しているという説もあります。
乗馬をしている人はご存じかもしれませんが、馬場を囲っている柵のことは今でも「埒」といいます。競馬のコースを囲っている柵も、関係者や乗馬ファンは埒と呼んでいますね。この埒が開かないと、馬が入ってこないので競争が始まりませんね。もしくは、競馬に限らず馬場でも、埒が開かなければ馬は外に出ることができません。
こうした馬の様子から、「物事に動きがないこと」や「出口が見えない状況」を埒があかないと表現するようになったのでは?と解釈されることがあるんです。ただし、「あかない」は「開かない」ではなく「明かない」という表記が正しいとされることが多い点には注意してくださいね。
余談ですが、埒が明かない=競馬のスタートの柵が開かないのでレースが始まらない様子という解釈もあるようです。しかし、発馬機の扉を埒と呼ぶことはあまりなく、また扉が開いて一斉にスタート!という形式も比較的最近の話。一方「埒明くる」という言葉は、すでに江戸時代の書物には見られるそうなので、これは俗説かもしれませんね。
まとめ
普段みなさんが何気なく使っている言葉のなかには、実は馬に関する文化が語源となっているものが少なくありません。こうしたことからも、かつて馬が人間の生活になくてはならない存在だったことがうかがえますね。今回紹介した以外にも馬にまつわる言葉はたくさんあるので、ぜひ探してみてはいかがでしょうか?