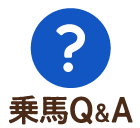馬への負担を最小限にする裏掘りのやり方

乗馬を始めると覚えないといけないことがたくさんあります。そのうちの一つが裏堀りです。今回は、我流になりがちな裏堀りの正しいやり方についておさらいをしましょう。また、馬への負担をすくなくするポイントについても紹介します。是非、この機会に裏堀りをマスターしましょう!
まずは裏掘りの重要性をおさらい

蹄は第二の心臓と言われるほど、馬にとっては重要な部位です。地面に蹄がつくタイミングで蹄が広がり、地面から蹄を上げたタイミングで蹄が収縮します。これを蹄機作用と呼びます。この作用によって、足元の血液を体に循環させるポンプの役割を果たします。そのため、蹄の部分から細菌などが入ってしまうと、血液に乗って循環してしまう可能性があります。
そのため、蹄につまったボロや寝ワラなどを取り除き、常に清潔にしておく必要があります。また、裏掘りをコンスタントにしていれば、蹄に何かしらの異常があってもすぐに発見することができます。裏掘りをする際に肢の他の部分にも触れるため、蹄だけではなく、肢全体に発症した異常を見つけるきっかけになることもあります。
やり方(準備編)

裏掘りをする前に準備をしましょう。基本的に裏堀りは放牧する前後、乗馬をする前後などに行います。汚れていない洗い場に馬を繋いで、テッピを準備しましょう。できれば、乾いた洗い場を使うことをおすすめします。また、泥がついてしまった場合は裏堀りをしたあとに水洗いすることをおすすめします。水洗いをする場合には、タオルや蹄油も準備しましょう。蹄のほかにも、特に繋の裏の部分はタオルでしっかりと拭きとる必要があります。水分をしっかりとふき取れたら、乾燥予防のために蹄油を塗ってあげます。
やり方(実践編)

裏掘りの基本的な方法も復習しておきましょう。左前肢から始めます。馬の左前肢の横で馬体と平行になるように後ろ向きに立ちます。横に立った状態で蹄を上げてもらうために、肩(前肢の付け根あたり)から蹄まで手を滑らせるようになでてみたり、左前肢をポンポンとしてみたり、左肩で馬の肩(前肢の付け根あたり)を軽く押したりします。できるだけ、その馬にとって負担にならない方法で肢を上げてもらいましょう。馬が蹄を上げたら、前肢と後肢の間から腕を回し入れるようにして、蹄冠と蹄壁あたりを手のひらで支えるように持ちます。できるだけ、馬に自発的に肢を上げてもらえるように心がけましょう。左前肢の裏堀りが済んだら、同じ位置から右前肢を触ると肢を上げてくれます。上げてくれない馬の場合は右側に移動して、右肩で軽く押したりしてみましょう。
後肢も基本的には同じです。背中からお尻、後肢となでるようにしたり、左肩で少し押したりすると肢を上げてくれます。このときに後肢を動かしたり、蹴ろうとするそぶりを見せりする馬もいます。肢を持ち上げてくれたら、すぐに蹄の内側から手を入れて蹄を支えて、馬が安定して立ちやすい後ろの方に肢を少し伸ばした位置で裏堀りをするのがいいでしょう。
蹄を持てたら、V字にくぼんでいる蹄叉側溝を掘って、ごみを掻き出します。次に蹄鉄に沿って、ごみを取り除きましょう。このときに、馬が暴れてしまうと危険なので、テッピは必ず手前側から奥に向けて動かすようにしましょう。ある程度、力を入れて、一気にごみを取り除きます。また、蹄叉の真ん中になる溝(蹄叉中溝)にゴミが詰まっている場合も取り除いてください。硬いゴミやボロなどをきれいに取り除いたら、砂などの細かいゴミを払うためにテッピについているブラシ部分を使って、きれいにします。きれいになったら、手を放して馬の肢を下ろします。
注意事項

自分の足を踏まれないように気を付けましょう。馬の体と平行に横に立つのがポイントです。蹄の前に自分の足を置かないようにします。馬の肢を下ろす前に、自分の左足の位置を確認しましょう。
また、夏場は虫が多いので、要注意です。身体が馬に対して斜めになっている状態で裏堀りをしていると、下をむいたときに頭が下がってしまって、蹄を下ろした瞬間に体にたかった虫を払おうとした馬の後肢に頭を蹴られてしまうことがあります。必ず馬体と平行に立ちましょう。
裏掘りをしている際に蹄をのぞき込んでしまうと、頭の位置が低くなってしまい、やはり頭を蹴られるリスクが高くなってしまいます。蹄をしっかり持って、自分の膝あたりの高さの位置で支えて裏堀りをするようにしましょう。
蹄叉を傷つけないように気を付けましょう。くぼんだV字の内側にある柔らかく盛り上がった部分です。勢いが余ってしまうとテッピが刺さってしまうこともないとは言いきれません。こういった怪我を防ぐためにも、テッピは必ず手前から奥に動かすようにしましょう。
1日に1回は蹄を水洗いをして、蹄油を塗ってあげましょう。蹄油を塗ると乾燥を防ぐことも、余分な水分を吸収することも防ぐことができます。また、冬場にお湯を使う場合は温度に注意が必要です。あまり温度の高いお湯を使ってしまうと、必要以上に蹄がふやけてしまい、弱くなってしまったり、乾燥しすぎてしまったりします。
蹄を不潔なままにしておくと、蹄叉腐乱を起こしてしまったり、小さな傷から細菌が入るなどして重篤な症状を発症し、命にかかわる事態になりかねません。蹄や肢をきれいにしながら、ケガはないか、腫れはないか、熱感はないかなども確認します。何かあれば、すぐに獣医師に相談しましょう。
裏堀りが嫌いな馬や苦手な馬もいます。できるだけ手早く済ませてあげるのがいいでしょう。特に高齢の馬の場合、3本肢で立っているのが苦手なこともあります。少しずつ慣れていって、手早く済ませるようにしましょう。裏掘りが終わったら、たくさん褒めてあげてください。
まとめ
今回は裏堀りについて、深掘りしてみました。普段、何気なく行っている裏堀りですが、馬の健康維持のために大切なお手入れです。ポイントは馬に合った方法で自発的に肢を上げてもらうことです。肢を上げてくれたら、馬が立ちやすくてリラックスできる位置ですばやく保定して、できるだけ手早く済ませましょう。馬にも人にも負担がかからない優しい裏堀りを目指したいですね。